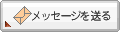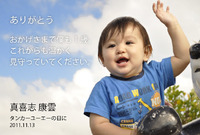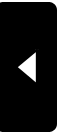2007年04月12日
東京ミッドタウン
前日がオープンだとも知らずに、ふらりと東京ミッドタウンに足を運んでいました。
未だ六本木ヒルズもタワーではなく、ゲートタワーのTUTAYAくらいしか行ったことがないというのに(笑)
確かにオシャレです!デカイです!ステキです!
でも...。
もう、こういう物質的な「何か」は僕の心には響かないようです。
久々の東京で疲れていたこともあるかも知れませんが...。
確かに田舎では見ることのできない建築・ショップ・グッズ・ディスプレイ・印刷物、刺激されるものはたくさんあるのですが、なんだか「虚しい」んですよね。
とか、いいつつ...。
いくつか気になったショップ・グッズが(笑)
一つめ。何と、お箸専門店!
最近、吉田雅紀さんの影響で「マイ箸」が欲しいなんて思っていたので、「おお〜っ!」と大感激で入ってみたものの...高い!
黒檀・紫檀・楓など、いい材木を一つ一つ手で加工した一品、なのは重々承知なのですが、今の僕には、お箸一膳10,000円以上〜はムリです。
金属製のものも置いてくれてればよかったなあ。
# ひょっとしたらあったのかも知れませんが、閉店時間で無情にも追い出され、
# 探しきれませんでした。;-p
箸長
—東京ミッドタウンオフィシャルサイト
 二つめ。「FRANCESCA GIOBBI(フランチェスカ・ジョッビ)」の靴。
二つめ。「FRANCESCA GIOBBI(フランチェスカ・ジョッビ)」の靴。女性ものですが、何よりもそのカラーリングとシルエットにほれぼれ。
こちらも一つ一つ手作りとのことだったんですが、靴だったら100,000円〜でも安い!と思えました。
内覧会で一足お先にチェック
『東京ミッドタウン』おすすめショップ【後編】
—カフェグローブ
まあ、ミッドタウンでなくても買えるんでしょうけれど、地下1階の雑貨コーナーで発見&試食。
ガンダーラの六億年前の塩など、まるで宝石のような岩塩の固まり(展示用)にビックリ。
ミッドタウンで買ったのはこれだけ!でした。
塩なのに、塩味以外の味がするんです。
僕のお気に入りはブラックロックソルト。
塩からゆで卵のような硫黄の香りがするんですよ。
料理によっちゃ、これだけでいいんではないか?と思わせられる様な香ばしさと濃厚な味でした。
Salt
—FAR EAST BAZAAR(ミッドタウンに出店していたお店)
とまあ、モノ至上主義に異論を唱えつつも、矛盾を承知でそれなりに楽しんで来た東京ミッドタウン探訪記でした(笑)
2007年04月11日
清明祭(シーミー)
シーミーとは...
簡単に言うと、ご先祖様(ウヤファーフジ)のお墓参の前に家族・一族・親戚が集まり、ピクニックをするイベントです(笑)。
こないだ参加してきたのは大本家(ウフムートゥヤー)と呼ばれる「一族」のシーミーでした。
僕の一族は、ルーツから「又吉」「真喜志」をはじめとした13の姓に分かれています。
沖縄には(ルーツの)各姓ごとに名前の一文字目を結びつける「名乗頭(なのりがしら)」という文化が残っているため、同姓同名の親族に出会う機会も非常に高いです。
昨年は同姓同名のおじいさんにお会いして、とても感慨深かったです。
名乗頭とは
—沖縄大百科
それにしても、沖縄の家族の単位の大きいこと!
僕のおばさんは「門中(もんちゅう)」と呼ばれる親族の大元、大きな仏壇のある家に嫁いだのですが、盆暮正月、シーミーの際には見たこともない遠い親戚の人々が手みやげを持って家に訪れます。
子供の頃は、よくお正月に潜り込んで、知らない人からお年玉をもらいまくってました(笑)
まあ、このようにして配り歩く先が多いため、お年玉一袋当たりの金額は500円〜1,000円と少ないのですが(笑)
さて肝心のシーミーについては...
僕の実のおじさんが、ブログに非常に丁寧に書いて下さってますので、ちょっと手抜きしてそちらにお任せしたいと思います(笑)
シーミー(清明祭)
—沖縄のヒロシです
さて今月は。
大本家、中本家の他に、親族のシーミーがある、シーミー月間です。
そんなことを考えながら大本家のお墓を眺めていたら...。
くだらないダジャレを思いついてしまいました。
「シーミー」読みを英語に置き換えると「See Me.」。
ご先祖様が「俺に会いにこい」と言ってるのかな?
お後がよろしいようで(笑)
# 正しくは「See Us.」かな?
2007年04月10日
すごい会議
 発刊されてしばらく経つ本ですが...。
発刊されてしばらく経つ本ですが...。大橋禅太郎さん著の「すごい会議-短期間で会社が劇的に変わる!
友達から「ぜひ教えて欲しい!」との声があったのでご紹介させていただきます。
インターネットの黎明期に、アメリカはシリコンバレーでITのベンチャー企業を起すことになった著者、大橋禅太郎さん。
この本は、山あり谷あり、涙と汗と感動のベンチャー起業記であると同時に、昨今話題になっている「コーチング」のすごさを教えてくれる本でもあります。
実は僕がこの本を最初に手に取った動機は、起業記が読みたかったわけでも、コーチングについて知りたいと思ったわけでもありません。
(そもそも、大橋禅太郎さんがこの本を出版されるまで、「コーチング」がここまで取り沙汰されることはなかった様に思います。)
ただ単純に「会議」が嫌いだったからです。
2〜3時間に渡って繰り広げられる不毛な「会議」。
終わってみれば、その時間に滞ってしまった仕事の山と、えも言われぬ疲労感だけ。
「結局今の会議で何が決まった?」
「次の会議の日程を取り付けただけ?」
そんな会議に心から嫌気がさしていたのです。
そこへ「すごい会議
そんな心理状況でこんなタイトルの本を見たら、手に取って読まぬわけにはいかないですよね(笑)
影響を受けやすい僕は、2005年の夏、当時の部下1名と大学生インターンシップ生3人とで早速この「すごい会議
...すごい。
会議を終えた後のみんなの達成感と使命感。
なんともさわやかな気分で仕事に取り組み直すことができた感動を今でもはっきり覚えています。
起業してからは...「忙しい」を理由に一度もこの「すごい会議
ようやく自分たちが考え、自分たちで作る仕事を進められる余裕ができて来たので、近々ぜひ実践してみたいと思います。
今本屋さんに行けば、溢れかえるほど「コーチング」の本が出ていますが、コーチングに興味がある人もそうでない人も、この本をまず一度読んでいただきたいと思います。
ちなみにこの本は大好評だったらしく、「すごい起業 絶頂と奈落のベンチャー企業「ガズーバ」
ちなみに僕は両方とも持っています。
2007年04月09日
LUNCH de DOSHA
今日は沖縄国際大学で予想以上の売上だったとかで、ご飯が売り切れ。
ほっかほっか亭でご飯を買って来て、店主のハナちゃんを交えてランチタイム。
トッピングも一部品薄というこもあり、全トッピングをケースごと持ち込んでもらって、セルフスタイルでいただきまーす。
2007年04月07日
琉球海炎祭2007
日本一早い夏の花火大会だそうです!
帰沖した一昨年はちょうど東京出張。
去年は東京から友達が来沖。
# 会場が家から近いので、終わりがけに一緒に遠くからちょこっと見ましたが...。
そんなこんなで3年目にしてようやく念願叶います!
今年はてぃーだショップさんにて限定コラボTシャツ付き優待チケットをゲットして準備万端!
# Tシャツはどうしても必要というわけではなかったのですが、
# 「龍」球インク社長としては、このデザインを見せつけられたら...ねぇ(笑)
いよいよ来週ですよ〜。
日本で一番早い夏、先取りして来ちゃいま〜す。
チケットまだの方はぜひぜひお早めに(笑)
琉球海炎祭2007チケット情報
—琉球海炎祭2007 オフィシャルサイト
2007年04月07日
Candle Night
上京中お世話になったみなさま、留守を守ってくれた社員のみんな、本当にありがとうございます。
今日は昨年Webサイトを制作させていただいたシルバーアクセサリブランド「GARNI」のフレグランスキャンドルを灯しながら家でお仕事。
上京中にGARNIのNさん、共通のお友達でディレクションをしてくださったAさん、社員のMk-10くんと一緒にお食事をしたんですが、その時お土産でいただいたキャンドル。
GARNIさん、こんな商品も出されているんですね〜。ビックリ。
香りもデザインもさすが!といった上品さ。
Nさん、ステキなお土産ありがとうございます〜。
もちろん、久々に会って楽しい時間を共有してくださったAさんも。
GARNIのこだわりの品の数々はどれもとてもステキなんですが、中でも僕のお気に入りは「Love Rings」。
Nさんにも「その時は絶対GARNIで作ってもらいます!」と約束して来ました(笑)
もちろん快諾してもらいましたよ〜。
カスタムメイドでこのデザイン、なのにこのお値段、絶対に安いです!
2007年04月06日
蒲田!
 ノミュニケーション!
ノミュニケーション!新宿二丁目より今ホテルへ帰りです。
と言っても、朝6:55分の飛行機なので、寝る時間はありませんが…。
Posted by maxi at
04:24
│Comments(0)
2007年04月05日
電車
 半年ぶりに東京で電車に乗って思ったこと。
半年ぶりに東京で電車に乗って思ったこと。こんな乗り物に依存しないと経済活動を行えない国が、本当の意味で豊かで美しい国になどなれるはずがない。
なんだか悲しくなりました。
僕はもともと期間限定のつもりで上京してましたから何とか堪えられましたが、そうでない人たちはみんな、よく心のバランスを保っていられるなあと感心します。
もちろん堪えられない人が増えてきて、少しずつ歪みが生じてきているわけですが…
Posted by maxi at
16:20
│Comments(0)
2007年04月05日
目黒
 権之助坂下の橋から雅敘園方面をのぞむ。
権之助坂下の橋から雅敘園方面をのぞむ。ここでも桜がきれいです。
目黒の社長さんとはある企みを進行中で、成功すれば相当ハッピーになれそうなんです。
引き続き頑張ろっと♪
Posted by maxi at
15:44
│Comments(0)
2007年04月05日
新宿駅南口
 やっぱり慣れ親しんだ街は安心するなあ。
やっぱり慣れ親しんだ街は安心するなあ。これからしゃぶしゃぶランチミーティングです♪
ちょっと期待してましたが、南口の工事は完了してないようです。
Posted by maxi at
11:30
│Comments(0)
2007年04月04日
御茶ノ水
 余裕を持たせまくってスケジュールを組んだはずなのに、どうしてこうなる…???
余裕を持たせまくってスケジュールを組んだはずなのに、どうしてこうなる…???出張は本当に怖いです。
御茶ノ水午後3時50分。
雨の影響で急に夜のごとく真っ暗です。
Posted by maxi at
16:00
│Comments(0)
2007年04月03日
東京丸の内
 今日の東京は寒い!
今日の東京は寒い!と思ったら、沖縄も寒そうですね。
毎日こうも寒暖の差が激しいと体がビックリしちゃいますね。
みなさんもお体ご自愛ください。
Posted by maxi at
17:11
│Comments(0)
2007年04月02日
中目黒にて
 あいにくの曇り空ですが、桜はやっぱりキレイ。
あいにくの曇り空ですが、桜はやっぱりキレイ。中目黒桜祭りは今週末の開催らしいですが、それまで散らずにいて欲しいですね!
Posted by maxi at
16:56
│Comments(2)
2007年04月02日
東京出張!
 実は今日から東京出張です。
実は今日から東京出張です。今は渋谷にて社員のMk-10くんを待ってます。
東京は桜の季節!
どこへ行ってもキレイです!
Posted by maxi at
10:53
│Comments(0)
2007年03月30日
あえて心を鬼にして
 ある沖縄県内の仕事にて。
ある沖縄県内の仕事にて。県内のサーバー業者さんから、サーバーへ接続するための情報(通称:FTP情報)がメールで送られて来ました。
メールというのは、色々なサーバーを経由して、最終的に手元に残ります。
その間経由して来たサーバーにもこの情報はコピーされて残ります。
ライブドアの事件からも見て取れる通り、堀江さんたちが手元PCのメールを削除した(と言われている)にも関わらず、検察がメールの情報を証拠として入手できたのはこのためです。
つまり、個人情報などが格納される恐れのあるサーバーへの鍵が、その気になればいつでも手に入れることができる状態になるわけです。
メールの傍受は比較的簡単であると言われており、知識のある人がその気になれば、やり取りの内容を誰にも気づかれずに盗み出すことも可能なわけです。
まあ、厳密な話をし始めると、このテーマだけで本1冊2冊は軽く書けてしまうくらいなので、ここでは割愛いたします。
# 僕もそこまで専門的な知識は持ち合わせておりません。
ということから、FTP情報というのはFAXを介してやり取りすることが、我々の業界の大原則となっています。
FAXはデジタルではなく、アナログの音声でのやり取りなので、傍受することはとても難しいと言われているからです。
このようなことは、僕の様なセキュリティの専門家でなくとも最低限知っていること。
まあ、個人向けサーバーのレンタルであればこれに限ったことではなく、メールで情報が流れてくることもありますが、今回はお国がらみのお仕事であるため、これは基本的にナシです。
このようなミスを放っておくと、いくら沖縄県が必至にIT産業を押し進めても、沖縄県のIT産業全体の信用を落とし、ひいては同じ業界で働く僕たちにも悪影響が及びかねません。
それどころか、国や県がせっかく多くの税金を投じて来たにも関わらず、いち産業として成り立たなくなってしまう可能性もあるわけです。
ということで、この業者さんにはあえて心を鬼にして苦言を呈しました。
これを無視、あるいは素直に受け入れないような業者さんであれば、僕は二度とこの業者さんのサービスを利用することはないでしょうし、同業他社がここを利用しようとしたときには「やめた方がいいですよ」とアドバイスするでしょう。
昨今の個人情報保護の風潮はいささか過熱気味で、各企業の経済活動へも大きな影響を与えているのではないか?やりすぎではないのか?と思うことも個人的には多々ありますが、今回の問題については最低限守らなくてはいけないことです。
経営者になって、守るべきものが増えました。
以前はなーなーに済ましていたであろうことも、厳しく指摘できる強さが身に付いてきました。
本当の優しさと本当の厳しさを持ち合わせた人になりたい。
大げさかも知れませんが、今回のこともそんな思いから出た行動です。
2007年03月29日
メッカフォン
 韓国はLG電子から2004年に発売されたという「メッカフォン」。
韓国はLG電子から2004年に発売されたという「メッカフォン」。きみは“メッカフォン”を知っているか?
—ライブドアニュース
その名の通り、イスラム教の人々が世界のどこにいても、礼拝時間とメッカの方向が分かるというケータイ。
記事は「宗教観が薄い日本人にとってはかなり驚きのアイテムです。」と締め括られていますが、本当にその通りですね。
で、僕が思いついたのは...。
「旧暦フォン」!
近年は以前に比べ意識が薄れつつあるものの、沖縄は未だ中国の文化を色濃く受けているため、年中行事はすべて旧暦で行われます。
僕が子供の頃は、お正月も新暦より旧暦の方を派手にお祝いしていたくらいです。
中国をはじめとして沖縄も、旧暦を重んじる場所に住む人々へ向けて、旧暦に特化したケータイが出たら便利なんじゃなかろうかと思いました。
沖縄では一門の仏壇を預かる家庭や、ユタと呼ばれるシャーマンの人々にとても重宝がられるはずです。
# 年末になると、コンビニに「沖縄手帳」という旧暦のイベントを詳細に記した手帳が売られているくらいですから。
暦について調べていたら面白い記事を発見しましたので、ついでに引用させていただきます。
現代に受け継がれる「旧暦」
—at home web
2007年03月29日
2007年03月28日
DOSHA店舗進出
 「タベテ、カラダ、キレイ」でおなじみDOSHAが、お友達の鈴木さんが4月から国際通りにて新たにオープンするバー「だいばぁずかふぇSUMMERSNOW」にコラボ企画進出!
「タベテ、カラダ、キレイ」でおなじみDOSHAが、お友達の鈴木さんが4月から国際通りにて新たにオープンするバー「だいばぁずかふぇSUMMERSNOW」にコラボ企画進出!とうとうお店でDOSHAのカレーが食べられるようになります。
# 実はこれに当たり、店主のハナちゃんからはちょくちょく相談を受けていました(笑)
DOSHAファンのみなさん、今後鈴木さんとDOSHAのブログを要チェックです!
ファンでなくても「以前から気になってた〜」という方も要チェックですよ〜!!
ちなみに龍球インクの面々は、DOSHAに出会ってからというもの、毎日建物にやって来る「超コッテリ格安弁当」が食べられなくなりました...。
だって、マズいし胃はもたれるし...そして太るんですもの...。
そのお陰で、DOSHAのやって来る木曜日以外のお昼は、車でお食事処探しの旅を続けておりましたが、最近は会社の近くに発見した居酒屋さんに入り浸っています。
しかし!その居酒屋さんは月曜日が定休日。
仕方なく月曜日だけは放浪を続けていましたが、「じゃあDOSHAに来てもらえばいいんじゃね?」ということになり、最近はほぼ毎週デリバリーをお願いしています。
DOSHAでは基本5食からデリバリーを受け付けてくれますので、沖縄本島中南部の方はぜひ同僚やお友達を誘って気軽にDOSHAを呼んでやってください〜。
DOSHAへのお問い合わせ・デリバリーはこちら
2007年03月28日
長編ドキュメンタリー映画「ひめゆり」
 ドキュメンタリー映画「ひめゆり」を那覇の桜坂劇場にて観賞しました。
ドキュメンタリー映画「ひめゆり」を那覇の桜坂劇場にて観賞しました。長編ドキュメンタリー映画「ひめゆり」
オフィシャルサイト
沖縄県民であれば、学校でテレビで、必ずと言っていいほど見聞きして来た「ひめゆり学徒隊」の悲劇。
あるいは「ひめゆりの塔」で、生き残りの方々の証言を聞いたかも知れません。
そんな悲劇のストーリーが、13年もの歳月を掛けて映画化されました。
どうして13年もの年月が掛かったのか?
それは、その体験があまりにも凄絶であったため、生き残られた元学徒たちが「忘れたい過去」を語るのに時間を要したからだそうです。
僕も何度かひめゆりの塔には訪れているはずですが、あまりに衝撃が大きすぎて、正直「近づきたくない」場所です。
ガイドをつとめる元学徒のみなさんが、毎度毎度過去を語るたびに涙に崩れ落ちる...。
そんな姿を見たのは、その場でだったのか、テレビを通してだったのかすら記憶が曖昧です。
体験していない僕ですら、ひめゆりの悲劇は「忘れたいこと」なのです。
今回もこの映画を観賞するにあたり、正直な気持ちとしては「観たくない」という気持ちの方が大きかったです。
しかし、なぜ観に行ったのか?
それは「観なければならない」からに他なりません。
しっかりと観て後世にこの悲劇を語り継ぐこと。
そして、沖縄戦を、ひめゆりの悲劇を知らない人々に知ってもらうことが沖縄を愛する者としての責務だと思ったからです。
こうして勇気を持って悲劇を語ってくれた元学徒のみなさん、そして「映画」という人々の心に届きやすい形として残してくださった監督ほかスタッフのみなさんに感謝。
まだこの映画を観ていない方、ぜひ観てください。
そして思ったこと、感じたことを誰かに話してください。
沖縄は桜坂劇場の他、東京でも上映が決定しているようです。
「ひめゆり」上映スケジュール
—オフィシャルサイト
予告編もありました。
長編ドキュメンタリー映画「ひめゆり」予告編
—オフィシャルサイト
最後に—。
公式パンフにも記載されているCoccoのステキな言葉を引用させていただきます。
映画の完成を待たずに3人の証言者が亡くなっている。
ひとつひとつ私たちは失くしていく。全てを失くす前に叶えたい。
おばぁたち、待っててね、なんにも分かっちゃいない私はせめておばぁたちが好きだった歌をうたおう。
鮮やかに見えるようだ。壕の中の笑い声。あなたが笑ってくれる歌を届けるからね。
“忘れたいこと”を話してくれてありがとう。
“忘れちゃいけないこと”を話してくれてありがとう。
—Cocco(毎日新聞『想い事。』より)
2007年03月27日
文才

人はファービーを好きになれるか?
—デイリーポータルZ
このコラム(?)を読んで吹き出さない人はいないはず!
ファービー。
昔懐かしいあのおもちゃ。
Wikipediaによると2005年にはファービー2が発売されたそうです。
かくいう僕もファービーベイビーを買ったことがありますが、飽きて人にあげてしまいました。
そんなファービーとマジメに向かい合ってみた、というこのコラム。
「文才」という言葉はこういう人のためにあるんだなあ、としみじみと感じました。
写真の挿入箇所や引用も絶妙。
そしてファービーの反応も絶妙。
久しぶりに腹を抱えて笑いました。